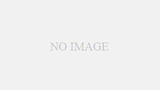部族社会の時代、東ヨーロッパの広大な大地には、定住農耕に長けたククテニ・トリポリエ文化と、馬の家畜化という革新を成し遂げたスレドニー・ストグ文化などのステップ文化が並存していました。この対照的な二つの世界は、紀元前4千年紀末から紀元前3千年紀にかけて、ヤムナ文化という巨大な遊牧民の波によって統合されることになります。
ヤムナ文化は、ポントス・カスピ海ステップで誕生し、馬と車輪という技術的優位性をもってユーラシア全土を席巻しました。彼らの拡大は、社会の階層分化と、現在約30億人の話者を有するインド・ヨーロッパ諸語の拡散という、ヨーロッパの根源的な社会変革を駆動しました。
ヤムナ文化:移動革命と階層分化の登場
ヤムナ文化(紀元前3300年頃~紀元前2600年頃)は、黒海北岸のステップ地帯、すなわち前時代のスレドニー・ストグ文化の領域で発展しました。彼らは、東ヨーロッパに「移動革命」と「階層分化」という二つの決定的な変化をもたらしました。
移動革命:乗馬と車輪の導入
前時代に馬の家畜化が始まっていたステップにおいて、ヤムナ文化は馬を究極の移動手段へと昇華させました。
- 乗馬による高速移動: 馬の背に跨ることで、一人の人間が一日で移動できる距離は飛躍的に伸びました。これにより、広大な資源を最大限に利用し、巨大な家畜の群れ(特に牛)を管理する移動牧畜という新たな生業が確立されました。移動牧畜によって、食料の季節変動や局所的な資源の枯渇という部族社会の根源的な「不安」を、移動という手段で完全にコントロールすることが可能になったのです。
- 荷車による大量輸送: 同時期にメソポタミアなどで発明された車輪と牛が牽引する荷車がステップにも導入されました。この技術は、ヤムナ文化に重い居住用テントや大量の物資を長距離運搬する能力を与え、彼らの遊牧生活をさらに大規模かつ組織的なものとし、数千キロメートルにも及ぶ民族的な移動を可能としました。
階層分化:クルガンの建設
ヤムナ文化の最も明確な考古学的特徴は、ステップ地帯に無数に残されたクルガン(墳丘墓)です。
- クルガンとは:巨大な墳丘墓のことであり、日本の古墳のようなものです。壮大な塚の下に権威ある個人の遺体を副葬品とともに葬ることで、祖先崇拝という精神的権威を物理的なランドマークとして永遠化する役割を果たしました。
- 副葬品と階層分化:クルガンからは、家畜(牛、羊、ヤギなど)の骨、銅の装飾品や武器、独特の土器(アンフォラ)、さらにはワゴン本体までが副葬品として発見されています。これらの副葬品の規模や質の差は、ヤムナ文化が比較的平等な部族社会から脱却し、富と権力が特定の指導者に集中する明確な階層分化が進んだ初期国家への移行期にあったことを示唆する考古学的な証拠となっています。
- 階層分化が発生した原因:家畜を基盤とする牧畜は、富が土地に固定される農耕社会とは異なり、階層分化を加速させました。牛などの家畜は生きたまま増殖し、移動できる富として機能したため、指導者層は複利的に富(家畜数)を増大させ、富の偏在を急速に強めました。この集中した富に、馬とワゴンによる高速移動能力(機動力) が結びついた結果、特定の指導者層は軍事的優位性を獲得しました。彼らはこの軍事力と機動性を利用して略奪や余剰生産物の独占を行い、富と権力をさらに集中させることで、ヤムナ社会に明確な階層分化をもたらしたのです。
ヤムナ文化の拡散:ヨーロッパの言語的・遺伝的基盤の形成
抜群の機動性、階層分化(強力な指導者層と軍事組織)、そして優れた武器を特徴とするヤムナ文化の拡大は、単なる遊牧民の季節的移動や小規模な移住にとどまらず、周辺地域への支配的な影響力を伴うものでした。
既存文化の終焉と構造的な不安の始まり
馬と車輪による高い機動性と銅製の武器、を持つヤムナ集団がユーラシア全土へと急速に拡散するにつれて、既存の農耕文化に決定的な影響を与えました。
- ククテニ・トリポリエ文化の衰退: 高度に発達していた東ヨーロッパのククテニ・トリポリエ文化は、紀元前3千年紀に入る頃に急速に衰退し、ヤムナ文化の勢力圏に吸収されました。これは、ヤムナの軍事的優位性に加え、当時の気候の寒冷化と乾燥化という複合的要因によるものでした。大規模な農耕に依存していたメガサイトが環境変化で「不安」を増大させたところに、乾燥に強く機動性のあるヤムナ集団の圧力が加わったのです。
- 征服と支配の出現: ヤムナ文化の拡大は、ヨーロッパ全土に人間関係と権力構造から生じる新たな不安をもたらしました。征服された地域では、比較的平等であった部族社会が崩壊し、ヤムナ集団に由来する支配階層と、先住の被支配階層という明確な階層分化が進みました。これは、後の国家へと続く、搾取と抑圧の構造的な「不安」の始まりでした。
インド・ヨーロッパ祖語(欧印祖語)の拡散
ヤムナ文化の拡大は、彼らが話していた言語の拡散を伴いました。この言語、インド・ヨーロッパ祖語(欧印祖語)は、現代の英語、ヒンディー語、ロシア語、ペルシア語など、約30億人の話者を有する世界最大の言語グループであるインド・ヨーロッパ諸語の共通の祖先と考えられています。
- 言語の証拠: 以下の表に見られるように、「母」や「新しい」といった基本的な単語が、数千年を経た現代の言語間でも規則的な音の対応を保っているのは、それらが共通の祖先言語から受け継がれ、変化を遂げた結果だと説明されます。(ヤムナ文化との関連は、考古学者マリヤ・ギンブタスが提唱したクルガン仮説によって裏付けられています。)
| 意味 | 英語 | ラテン語 | サンスクリット語 (インド) |
| 母 | Mother | Mater | Mātar |
| 新しい | New | Novus | Nava |
西方への拡大:縄目文土器文化の登場と初期国家の基礎
ヤムナ文化の影響は、文化的な接触や混交を通じて中央ヨーロッパにも波及し、新たな文化を生み出しました。
縄目文土器文化(Corded Ware culture, CWC)は、紀元前3200年頃から中央ヨーロッパに広範囲に拡大し、ヤムナ文化の直接的な影響を最も強く受けた文化とされています。
- ヤムナとの共通点: CWCは、遺伝的構成、埋葬習慣(クルガンに似た単独埋葬、戦闘斧の副葬)、そして馬の利用という点でヤムナ文化と共通していました。
- 言語と社会変革の担い手: 彼らは、ヤムナ集団から伝播したインド・ヨーロッパ祖語の北方方言(後のゲルマン語派、バルト・スラヴ語派の祖先)をヨーロッパに広めた主要な担い手と見なされています。また、男性の戦士の墓に重点が置かれるなど、軍事的指導者層の権力を確立させました。
まとめ
このヤムナ文化とそれに続くCWCの時代に確立された、武力と強制力に基づく権力、そして支配層と民衆の明確な階層分化は、部族社会の緩やかな統治システムでは解決しきれなかった新たな不安を伴いながらも、より大規模な集団を統率する初期国家の確固たる基礎となりました。彼らの足跡こそが、ヨーロッパにおける言語、遺伝、そして社会構造のルーツの一つなのです。
参考文献
ディヴィッド・W・アンソニー「馬・車輪・言語」(2018)筑摩書房
宇山卓栄「世界『民族』全史」(2023)日本実業出版社
< 前へ 次へ >