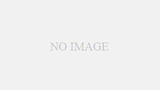人類の歴史は、私たちを駆り立てる根源的な不安と、それを何とかコントロールしたいという飽くなき欲求の物語です。
西アジアの「肥沃な三日月地帯」で始まった農業革命という変革の波は、紀元前7千年紀頃から徐々にヨーロッパへと伝播し、広大な東ヨーロッパの風景を一変させました。 前時代の移動型狩猟採集生活(バンド社会)から、定住を基盤とする部族社会への移行は、食料確保のあり方を根底から変え、私たちの祖先が抱える不安の質を大きく変化させました。
東ヨーロッパの部族社会は、その地理的特殊性(肥沃な黒土地帯・カルパティア山脈の森・無限に広がる黒海北岸のステップ)ゆえに、他の地域とは異なる、二つの異なる進化を辿ることになります。
完新世で誕生した東ヨーロッパの地理的特殊性
約1万年前、最終氷期が終わり、地球は温暖な完新世へと移行しました。この気候変動は、東ヨーロッパの環境に決定的な変化をもたらしました。
豊かな生態系と定住への誘惑
気温の上昇と降雨量の増加により、ヨーロッパ全域で豊かな森林が広がりました。しかし、東ヨーロッパでは特に、ポントス・カスピ海ステップという広大な草原地帯が、野生のウマやウシ、その他の家畜化に適した動物の宝庫となりました。一方、その西側のドナウ川流域やカルパティア山脈周辺では、西アジア起源の野生の穀物(小麦、大麦など)の栽培に適した肥沃な土地が広がっていました。
バンド社会の移動型狩猟採集民にとって、食料不足の不安は常に根源的なものでした。完新世の到来により、特定の場所で安定的に食料が得られることが分かってくると、彼らの中で新たなコントロール欲求が芽生えます。それは、「この豊富な食料を、この場所でずっと手に入れることはできないだろうか?」という食料の安定確保への強い願望でした。
定住化の萌芽と人口増加の圧力
食料が比較的安定して得られるようになると、人類の人口は徐々に増加し始めました。定住の兆しは、移動生活の制約から解放され、より多くの子供を育てることを可能にしました。この人口増加は、やがて既存の狩猟採集生活だけでは増え続ける人口を支えきれないという、新たな不安を生み出しました。この不安こそが、東ヨーロッパにおける農耕と牧畜という二つの異なる道筋での農業革命を駆動したのです。
農業革命の伝播:並行する2つの道筋
中東の農耕技術は、バルカン半島の初期農耕文化(スターチェヴォ文化など)を共通の源流として、東ヨーロッパへと伝わりました。しかし、その受容と発展の仕方は、大きく2つの流れで広がりました。
中央ヨーロッパへの伝播
肥沃な土地を求めてドナウ川沿いを西進し、中央ヨーロッパへと農耕を定着・拡散させた経路です。
クリッシュ文化(ドナウ川上流域への第一波)
紀元前6200年頃からドナウ川を遡上し、カルパティア盆地に入った初期の新石器文化です。小麦や大麦の栽培、牛や羊の飼育を取り入れ、河川沿いに定住集落を築き、根源的な「食料不足の不安」を大幅にコントロールできるようになりました。
線帯文土器文化(中央ヨーロッパへの拡散)
紀元前5500年頃から中央ヨーロッパ全域へと大拡散した文化です。数百人規模の定住的な部族社会を形成しました。主な不安は、豊作・不作という自然の不確実性と、土地と資源を巡る隣接集団との争いでした。彼らは、祖先崇拝や地母神信仰といった新たな権威を生み出し、共同体の結束と農耕の安定を願ったのです。
東ヨーロッパ内陸部への伝播
カルパティア山脈の東側、現在のウクライナ西部で独自の発展を遂げた経路です。
ククテニ・トリポリエ文化(東欧農耕の頂点)
紀元前5500年頃から紀元前2750年頃にかけて栄えました。色彩豊かな彩文土器と、最大で数万人規模に達する巨大なメガサイト(巨大集落)を特徴としました。彼らが直面した不安は、これほど大規模な集団を維持するための共同体内部の秩序維持や食料の公平な分配といった、より複雑な問題でした。
ククテニ・トリポリエ文化では、巨大集落を数十年おきに焼却し、新しい集落を築き直すという独特の循環が見られます。この現象については諸説ありますが、一部の研究者は、社会的緊張や不安をリセットするための象徴的な再生儀礼であった可能性を指摘しています。
ステップ地帯の独自進化:馬の家畜化と環境への適応
ヨーロッパ内陸の農耕文化が定住と共同体管理の技術を発達させる一方、黒海北岸のステップ地帯では、環境に応じて全く異なる方向で「不安」をコントロールする試みが進んでいました。
ステップの「不安」と環境圧力
完新世に移行しても、ステップ地帯は冬の厳しさや周期的な乾燥といった大きな環境不安を抱えていました。特に、ウマは豊富に存在しましたが、素早く、巨大な群れで移動するため、持続的な食料供給源とするには困難がありました。この厳しい環境圧力こそが、彼らに食料を安定供給し、かつ広範囲を移動できる「究極の手段」を求める強い動機を与えました。
スレドニー・ストグ文化(寒冷・乾燥への適応と馬の家畜化)
東ヨーロッパのステップ地帯、特にウクライナのドニエプル川周辺では、人類とウマの関係に劇的な変化が生じました。紀元前4200年頃~紀元前3800年頃に気候が寒冷化したため、その頃に栄えたスレドニー・ストグ文化において、後の遊牧の基盤となる馬の家畜化が進んだと考えられています。
- 寒冷なステップでの馬の優位性: 馬はウシなどの他の家畜に比べ、寒冷や乾燥に強く、硬い草を雪の下から掘り出して食べる能力(雪中採食)に優れているため、雪の降る状況では飼育が容易でした。
- 馬の利用の加速: 彼らの遺跡からは、馬の家畜化の初期段階を示す証拠が得られています。馬の利用技術は、ステップの部族社会にとって究極の「コントロール欲求」の実現でした。
スレドニー・ストグ文化は、この馬の特性に着目し、馬の利用を加速させることで、厳しいステップ環境下でも安定して食料と移動性を確保するという新たなコントロール欲求を実現し、後のヤムナ文化による大規模な移動牧畜の基盤を築きました。
(補足:現在最も有力な乗馬の起源地として紀元前4千年紀中頃に繁栄した中央アジアのボタイ文化が知られています)
まとめ
この時期の東ヨーロッパは、二つの異なる部族社会が共存していました。
- 定住農耕部族社会: 西の線帯文土器文化(LBK)とその系統、そして東のククテニ・トリポリエ文化。安定した土地と共同作業を基盤とする。
- 移動牧畜部族社会: 東のステップ地帯の文化(スレドニー・ストグ文化など)。寒冷・乾燥といった環境圧力への適応を強く求められる中で、馬という新たな技術と移動性を基盤とする。
この二つの社会は、互いに交流し、緊張関係を保ちながら、東ヨーロッパという巨大な舞台で共存しました。そして、ステップ地帯で生まれた「馬のコントロール」という革新は、やがて来るべきヤムナ文化の時代に、ユーラシア大陸全土を巻き込む巨大な社会変革のエネルギーとなるのです。
参考文献
ディヴィッド・W・アンソニー「馬・車輪・言語」(2018)筑摩書房
宇山卓栄「世界『民族』全史」(2023)日本実業出版社