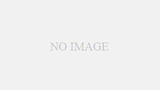人類史を、根源的な「不安」とそれを「コントロール」しようとする飽くなき欲求の物語として読み解く本ブログ。
今回は、人類が地球上に登場して間もない頃、血縁を中心とした小さな集団で暮らしていたバンド社会(旧石器時代)に焦点を当てます。この時代は、私たちが抱える不安の原型が生まれ、それを乗り越えるための最初の試みが行われた、人類史の壮大な物語の序章です。
この壮大な物語の舞台の一つ、東ヨーロッパはどのような状況だったのかを紐解いていきましょう。
ホモ・サピエンス登場以前
東ヨーロッパの広大な平原と冷涼な気候は、はるか昔から生命を育む舞台でした。この地に確かな人類の足跡が刻まれたのは、数十万年前にさかのぼります。
例えば、約40万年~4万年前に生息していたネアンデルタール人の人骨は、クロアチアのクラピナ遺跡やハンガリーのスバリュク洞窟、ウクライナのキーク・コバ洞窟など、東欧各地から広範囲にわたって発見されています。彼らは強靭な体躯でヨーロッパの寒冷な気候を生き抜いた人類です。
【参考】ナショナル ジオグラフィック日本版:ネアンデルタール人、どんなヒトだったのか なぜ絶滅?
さらに、彼らよりもはるかに古い時代、南のコーカサス地方・ジョージアのドマニシ遺跡では、およそ180万年~160万年前というきわめて古いホモ・エレクトスやその初期段階と考えられる人類化石が見つかっています。これは、人類のユーラシア大陸への拡散が非常に古くから始まっていたことを示唆しています。
【参考】ナショナル ジオグラフィック日本版:ドマニシ原人の遺跡から犬の化石、リカオンに近縁か
彼らの生活は、現代の私たちには想像もつかないほど過酷なものでした。食料はすべて自然に依存し、いつ獲物にありつけるか分からない。ホラアナライオンやハイエナといった強力な捕食動物に脅かされ、またマンモスのような巨大動物との遭遇も危険を伴いました。気候変動や病気、ケガなど、生存を脅かす無数の不確実性に直面し、彼らはハンドアックスやチョッパーのような単純な石器を唯一の武器として生き抜いていました。
この時代の彼らが抱えていた不安は、まさに生存そのものに対する根源的な不安だったと言えるでしょう。
ホモ・サピエンスの登場
約4万年前、ユーラシア大陸の西端にいたホモ・サピエンスが、東欧の地に足を踏み入れます。彼らは、より高度な思考能力と創造性を持つ存在でした。彼らの到来は、この地域の歴史に大きな変革をもたらします。
道具と居住におけるコントロール
ホモ・サピエンスは、寒冷地で入手可能な資源を活用する知恵を持っていました。コステンキ遺跡やウクライナのメジリチ遺跡など、ロシア・ウクライナ周辺からは、巨大なマンモスの骨でできた住居跡が数多く見つかっています。これらは、寒さを凌ぐための実用的な住居であると同時に、部族のシンボルとして象徴的な意味を持った可能性も指摘されています。
さらに、彼らの道具は、それ以前の人類のものよりも格段に洗練されていました。骨や象牙を加工したナイフ、槍の穂先、そして縫い物をするための針など、より多様で精巧な道具を製作していました。これは、彼らが単なる生存のための道具作りを超え、より複雑な思考や技術を持っていたことを示します。
アニミズムと儀式によるコントロール
ホモ・サピエンスは、単なる生存技術の進化を超え、目に見えない世界に「意味」を見出し、それを理解し、コントロールしようと試み始めました。これは、精神的な不安を和らげるための重要な一歩でした。
ロシアのコステンキ遺跡からは、マンモスの牙に乳房や尻の部分を誇張して彫ったヴィーナス像が出土しています。また、チェコで発見された「ヴェストニツェのヴィーナス」に代表されるこれらの女性像は、生命や豊穣への強い願望を象徴しています。食料の確保が困難な東欧の寒冷な環境において「種の存続」に対する根源的な不安が、このような地母神信仰という形で表現されたと考えられます。
さらに、コステンキ遺跡で見つかったマンモスの骨で作られた直径12メートルのボーンサークルは、単に食糧の加工・保存場所としてだけでなく、儀式的な用途があった可能性も指摘されています。
【参考】カラパイア:マンモスの骨で作られた2万5000年前の謎めいたボーンサークルが発見される
このような遺跡の証拠から、当時の人々は、自然の精霊や動物、祖先といった目に見えない存在と対話し、病気や災害の原因を探り、未来を予測しようとしたと推測されます。そして、部族の知恵と経験を一身に背負い、集団全体の不安を鎮めて導く、シャーマン的役割を担う人物がこの時代に登場し始めたと考えられます。
死と向き合う:儀式と「個」の認識
ホモ・サピエンスが他の人類と決定的に異なっていたのは、死者への接し方です。コステンキ遺跡からは墓址が確認されており、そのうちの1基の遺骸には赤色顔料が付着し、石器を副葬していました。
これは、死後の世界や魂の存在を信じていたことを示唆しています。死という圧倒的な不確実性、そして愛する者を失うという深い悲しみ。これらの不安を和らげるために、彼らは埋葬という儀式を生み出しました。それは、生き残った人々に心の安定をもたらし、肉体が滅んでも魂は部族を見守ってくれるという希望を与えたのです。また、これらの副葬品は、個々の人間が尊重され、そのアイデンティティが認識されていたことを示しており、後の社会における多様な役割分担につながる重要な要素となった可能性があります。
まとめ
バンド社会は、このようにして、生存に対する根源的な不安を、儀式や信仰、そしてシャーマンという役割を通じてコントロールしようと試みました。狩猟の成功を願い、病気の治癒を祈り、死後の世界を信じることで、彼らは集団としての結束を強め、過酷な環境を生き抜くための精神的な支えを築き上げていきました。
彼らが残した小さな住居跡や埋葬跡は、単なる考古学的な遺物ではありません。それは、私たちが今も抱える不安と向き合い、それを乗り越えようとする、人類の最初の物語なのです。
やがて最終氷期が終わり、農耕が始まると、人類は部族社会へと発展します。安定した食料供給という新たなコントロールを獲得した人類が、どのようにして社会の仕組みをさらに複雑化させていったのかを次回は紐解いていきましょう。